2025年8月13日
便に血が混じんでいる(血便)ことに気づくと、誰でも驚き心配になりますよね。血便には様々な原因がありますが、その一つに「大腸憩室出血」という病気があります。この記事では、大腸憩室出血とは何かを解説し、血便をきたす他の原因との鑑別ポイントや、診断に用いられる大腸カメラ(大腸内視鏡検査)や胃カメラの役割について、一般の方にも分かりやすく説明します。適切な受診行動につながるよう、専門医の視点からポイントを押さえていきましょう。
憩室とは何か?
まず「憩室」とは何でしょうか?大腸の憩室とは、大腸の壁の一部が外側に小さな袋状に突出したものです。いわば大腸の壁にできたポケットのような構造で、大腸壁の弱い部分(血管が貫いている場所など)に圧がかかることで生じると考えられています。加齢や慢性的な便秘により腸内の圧力が高まると憩室ができやすく、実際に高齢になるほど憩室を持つ人が増えています。また、日本では高齢化や血液をサラサラにする薬の使用増加に伴い、大腸憩室からの出血が下部消化管出血の原因として近年最も多くなってきているとの報告もあります。
憩室そのものは無症状であることが多く、持っているだけなら特に治療の必要はありません。しかし、憩室に炎症が起これば「憩室炎」、憩室から出血すれば「憩室出血」という合併症を引き起こす可能性があります。次に、この大腸憩室出血の特徴と症状について見ていきましょう。
大腸憩室出血の特徴と主な症状
大腸憩室出血とは、その名の通り大腸の憩室から出血する病態です。主な症状は突然の血便(鮮やかな赤色の出血)であり、特徴的なのは痛みをほとんど伴わずいきなり出血が起こる点です。腹痛などの前触れがなく、トイレの水が真っ赤に染まって初めて気づくケースもあります。驚く状況ですが、多くの場合この出血は自然に止まります(報告によれば自然止血率は70〜90%)。しかし油断はできません。一度止まったように見えても再び出血することがあり、実際に約3割の患者さんは1年以内に再出血を起こすとのデータがあります。まれにですが、大量出血して血圧が下がりショック状態に陥ることもあり、緊急の処置が必要になるケースも報告されています。
このように大腸憩室出血は主に高齢者にみられる疾患で、とくに抗血栓薬(いわゆる血液サラサラの薬)を内服中の方で起こりやすい傾向があります。出血自体は自然に止まることが多いとはいえ、原因を特定して適切に対処することが重要です。では、血便が見られる場合、憩室出血以外にどのような原因が考えられるのでしょうか?次の章で血便の鑑別診断について説明します。
血便の鑑別診断
血便をきたす主な原因には次のようなものがあります。大腸憩室出血と紛らわしい疾患もあるため、それぞれの特徴を押さえておきましょう。
・痔核(じかく)・裂肛(れっこう)
いわゆる痔(いぼ痔や切れ痔)です。肛門付近の静脈がうっ血してこぶ状になる痔核や、硬い便で肛門が切れてしまう裂肛では、排便時によく出血がみられます。痔による出血は鮮紅色でトイレットペーパーや便の表面に付着する程度の少量出血が多いですが、ときに噴き出すように出血することもあります。通常、痔の出血では血液が便と混ざらずに分離している点が特徴です(便の中ではなく表面や紙につく)。裂肛では強い痛みを伴うのも特徴です。一方、大腸憩室出血は痛みがない場合がほとんどなので、「鮮血だけど痛みがない」出血は痔ではなく憩室出血などを疑います。
・大腸ポリープ
大腸の粘膜から盛り上がるポリープでも出血することがあります。特に肛門に近い場所にポリープができていると、便がこすれることで出血して血便が出る場合があります。しかしポリープの場合、目で見て分かるほど大量の出血になることはほとんどありません。少量の出血でも見逃さないために便潜血検査が有用で、ポリープからのわずかな出血もこの検査で拾い上げ早期発見につなげることができます。
・大腸がん
大腸がんも重要な鑑別疾患です。早期の大腸がんはほとんど症状がありませんが、進行すると出血や便通異常(便秘・下痢が続く)、腹痛など様々な症状が現れます。特に直腸に近い部分のがんでは血便として発見されることが多く、便に鮮血が付着する形で出血が見られるのが特徴です。ただし裏を返せば、「血便に気づいた時点ではかなりがんが進行している場合が多い」ことも事実です。大腸がんは早期に発見し治療すれば治癒が期待できる病気です。肉眼では分からない微量の出血でも便潜血検査で検出できますので、痔だと決めつけず見逃さないことが大切です。
・虚血性腸炎(虚血性大腸炎)
虚血性腸炎は大腸の血流が低下して起こる炎症です。便秘で強くいきんだ時など一時的に腸の血流が悪くなることが引き金となり、高齢の女性に多くみられます。腹痛を伴い、下痢や便器の水が真っ赤に染まるほど大量の出血が生じることがあります。憩室出血と同じく高齢者に起こりやすい疾患ですが、虚血性腸炎では腹痛が強い点で無痛性の憩室出血と区別できます。多くは点滴治療で改善しますが、重症例では入院が必要です。
・その他の腸の病気
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患では、粘液や膿を伴う慢性的な血便や下痢がみられます。また、病原性大腸菌(O157など)による感染性腸炎でも激しい腹痛と血性の下痢(しぶり腹を伴う下痢に血が混じる)が起こることがあります。これらは発熱や他の症状を伴うことが多く、憩室出血(突然の無痛の出血)とは経過が異なります。
このように、血便の原因は多岐にわたります。素人判断で「おそらく痔だろう」と放置するのは非常に危険です。実際、「痔だと思っていたら実は大腸がんだった」というケースも報告されています。血便に気づいたら恥ずかしがらずに消化器科を受診し、必要な検査を受けることが重要です。特に40歳以上の方は症状がなくても年に1回は大腸がん検診(便潜血検査)を受けることが推奨されています。便潜血検査で陽性(便に血が混じむ疑い)が出た場合は、精密検査として大腸カメラ(大腸内視鏡検査)を必ず受けて精査するようにしましょう。
大腸カメラ・胃カメラの役割
血便の原因を調べるうえで、内視鏡検査は欠かせません。中でも大腸全体を直接観察できる大腸カメラ(大腸内視鏡検査)は非常に重要です。大腸カメラでは肛門から細長い内視鏡(カメラ)を挿入し、盲腸から直腸まで大腸粘膜をくまなく観察します。血便の原因である病変を直接目で確認できるため、診断の精度が高い検査です。たとえば大腸憩室出血であれば、内視鏡で出血源となった憩室を特定し、クリップで止血するなどその場で治療まで行うことも可能です。また大腸カメラでは、大腸ポリープが見つかればその場で切除することができますし、大腸がんが疑われる病変があれば一部を採取して顕微鏡で調べ(生検)、がんかどうか確認することもできます。このように大腸内視鏡検査は診断と治療を兼ねられる有用な検査なのです。
一方、胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)は食道・胃・十二指腸を調べる内視鏡検査です。通常、鮮紅色の血便がある場合は大腸からの出血を疑って先に大腸カメラを行います。しかし便が黒っぽいタール状(黒色便)の場合、胃や十二指腸からの出血(消化性潰瘍など)が疑われます。出血する場所によって便の色が異なり、肛門に近い大腸からの出血なら真っ赤な血便、胃や十二指腸からの出血ならタール様の黒色便になるためです。このような黒色便や吐血がある場合、胃カメラで上部消化管に出血源がないか調べます。また、大腸カメラをしても原因が特定できない時にも、見落としのないよう胃カメラを追加することがあります。消化管は口から肛門まで一続きの管なので、大腸に異常がない場合でも上部消化管(胃や食道)からの出血がタール便として現れることがあるわけです。
内視鏡検査と聞くと不安になる方もいるかもしれませんが、現在では鎮静剤を使用してうとうと眠ったような状態で検査を受けることも可能です。不安や痛みを和らげ、安全に検査を受けられるよう工夫されています。医師と相談のうえ、必要な検査を受けることで早期発見・早期治療につながりますので、怖がらずに受診してくださいね。
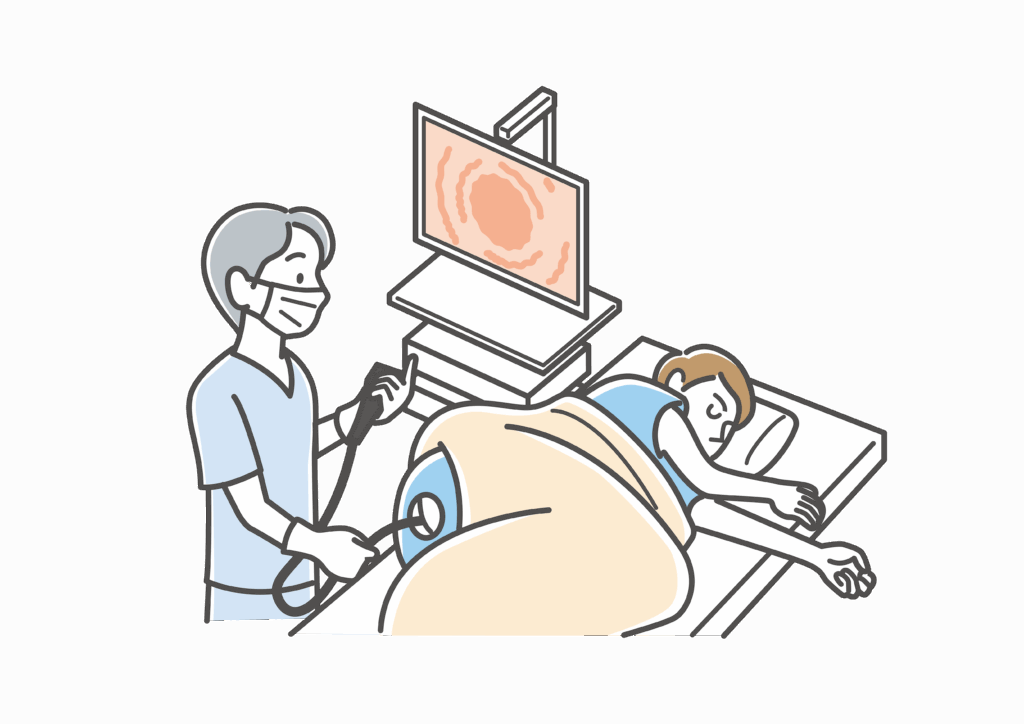
血便に気づいたら早めに受診を
繰り返しになりますが、便に血が混ざっていたら決して放置せず、早めに医療機関を受診しましょう。血便の裏には、痔のように心配の少ないものから大腸がんのように早急な治療が必要なものまで様々な病気が隠れています。特に「痔だから大丈夫」と自己判断して受診を先延ばしにすると、治せる段階のがんを見逃して病状を悪化させてしまう可能性も指摘されています。大腸がんは早期に発見し適切に治療すれば根治も期待できる病気ですから、チャンスを逃さないようにしたいですね。40代以上の方は症状の有無に関わらず定期的に検診を受けておくことが望ましいですが、少しでも気になる症状があれば年齢に関わらず専門医に相談してください。
血便という体からのサインを軽視せず、適切な検査(大腸カメラや胃カメラなど)で原因を調べてもらうことが健康への第一歩です。専門医による診断のもと、必要な治療を受ければ多くの場合は改善が期待できます。「もしかして大腸憩室出血かも?」と不安に感じたら、ぜひ早めに消化器科を受診して安心につなげましょう。



