2025年08月01日
機能性ディスペプシア(Functional Dyspepsia、略称 FD)は、胃もたれやみぞおちの痛みといった腹部の不快な症状が慢性的に続くにもかかわらず、内視鏡検査などで原因となる明らかな病気が見当たらない状態を指します。消化管に潰瘍や腫瘍など器質的異常がないにもかかわらず症状が起こることから、胃の働き(機能)の不調による疾患として「機能性ディスペプシア」と名付けられました。以前は原因不明の胃の不調をまとめて「慢性胃炎」と説明することもありましたが、必ずしも胃の炎症と症状が一致しないと分かり、現在では慢性胃炎とは別の概念としてFDが確立しています。
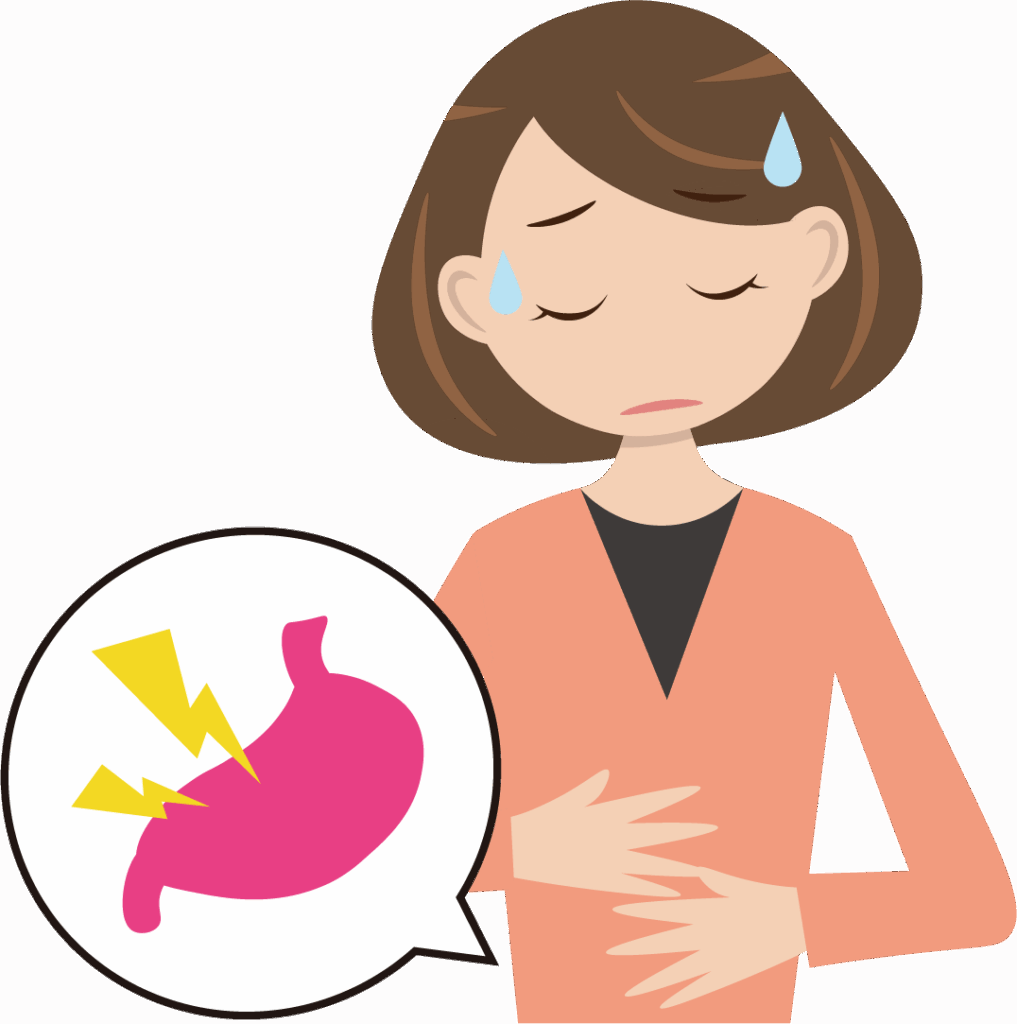
機能性ディスペプシアの症状と特徴
FDの代表的な症状には、みぞおちの痛み(心窩部痛)、焼けるような胃の不快感(灼熱感)、食後の胃もたれ(膨満感)、早期満腹感(普段と同じ量を食べきれず途中でお腹いっぱいになってしまう)などがあります。そのほか食欲不振やげっぷ、吐き気を感じる方もいます。症状は食事と関連して起こることが多いですが(食後に胃が重くなる、少量で満腹になる等)、空腹時でも上腹部の痛みやもたれ感を感じる場合もあります。これらの症状が日常的に繰り返し現れるため、「胃の調子がずっと悪い」状態が続くのがFDの特徴です。
症状が慢性的であることもFDの診断上重要です。国際的な診断基準であるローマIV基準では、症状が6か月以上前からあり、そのうち直近3か月間持続していることがFDの定義要件とされています。言い換えれば、一時的な胃もたれではなく半年以上にわたり症状が続いている場合にFDと考えます。また症状の程度には個人差がありますが、症状が強い患者さんでは生活の質(QOL)の低下が報告されており、適切な治療によって症状が和らげばQOLも回復するため早めの受診が勧められます。実際、症状がつらい人は我慢せず専門医に相談し、生活改善や薬物治療で症状のコントロールを図ることが大切です。
なお、FDは決して珍しい疾患ではありません。胃の不調を感じて病院を受診した人の約半数(45~53%)が検査で異常が見つからずFDと診断されたとの報告もあります。健診受診者を対象とした調査でも10~20%前後にFDの人がいたというデータがあり、FDは一般の人にもよくみられるありふれた病気です。
機能性ディスペプシアになりやすい人・原因
機能性ディスペプシアの原因は一つではなく、複数の要因が絡み合って発症すると考えられています。 主な要因として、以下のようなものが知られています。
・胃の運動機能異常
胃や十二指腸の運動(ぜん動運動)に障害があると、食べ物の胃から十二指腸への排出が遅れたり(※場合によっては早すぎたり)、食事に合わせて胃が十分に広がらず食べ物を溜めこめなくなったりします。その結果、食後に胃もたれや膨満感が生じたり、少量で満腹になる原因になります。
・消化管の知覚過敏
胃や十二指腸が過敏になり、通常なら刺激と感じないような弱い刺激でも不快症状が出やすくなった状態です。FD患者では健常者より少ない胃の伸展(膨らみ)刺激や温度刺激で痛み・もたれ感が生じることが報告されています。また十二指腸に流れた胃酸や脂肪に対しても過敏に反応し、症状を引き起こす場合があります。
・ストレスや心理的要因
脳腸相関といって脳と腸は密接に影響し合っています。不安や抑うつなどの心理的ストレス、あるいは幼少期の虐待経験といった心のトラウマがあると、胃腸の運動や感覚に変化が起こりやすくなることがわかっています。実際、FD患者では不安障害や抑うつ状態を合併することが少なくなく、ストレスが症状悪化の誘因となるケースもあります。
・胃酸による刺激
胃から分泌される強い酸が胃や十二指腸の粘膜を刺激し、運動機能や知覚過敏に影響を与える場合があります。特に胃酸に対する感受性が高い人では、少量の胃酸でもみぞおちの痛みにつながることがあります。
・ピロリ菌感染
ヘリコバクター・ピロリ菌(以下ピロリ菌)もFDの一因と考えられます。ピロリ菌感染により胃粘膜に慢性的な炎症が起こると、それが消化管機能に影響して症状を引き起こす可能性があります。実際にピロリ菌の除菌治療を行った後、半年~1年経ってFD症状が改善するケースでは、ピロリ菌感染が症状の原因であったと推定されます(※除菌直後に症状が劇的に良くなるわけではなく、炎症が治まるまで時間がかかるためです)。
・感染症をきっかけとする場合
サルモネラなどによる急性胃腸炎のあと、そのままFD様の症状が長引くことがあります。このように感染症が契機となって起こるFDを感染後機能性ディスペプシアと呼ぶことがあります。
・生活習慣の乱れ
喫煙や過度の飲酒、睡眠不足、不規則な食事時間や偏った食生活といった生活習慣もFD発症のリスク要因とされています。例えば喫煙者は非喫煙者に比べFD発症リスクが約1.5倍高いとの報告もあり、禁煙など生活習慣の改善が予防・症状改善に有用と考えられます。
・その他の要因
体質(遺伝的素因)も関与すると指摘されており、実際FDは女性にやや多い傾向が報告されています。また十二指腸の粘膜にわずかな炎症細胞の集積(微小炎症)が認められるケースもあり、こうした炎症による粘膜バリア機能の低下が症状に関与する可能性も示唆されています。腸内細菌叢の乱れ(ディスバイオシス)など、新たな要因についても研究が進められています。
機能性ディスペプシアの診断方法
FDは「除外診断」とも言われます。他の病気(胃潰瘍、胃炎、逆流性食道炎、胆石症、膵炎、胃がん等)ではないことを確認したうえで初めてFDと診断されるからです。医師は症状の経過や特徴を詳しく聞き取り、まず血液検査や画像検査で全身状態を評価します。その上で必要に応じて上部消化管内視鏡(胃カメラ)検査を行い、胃や十二指腸に器質的な異常(炎症・潰瘍・腫瘍など)がないか直接確認します。特に高齢者(一般に50歳以上)で新たに症状が出た場合や、体重減少・吐血といった警戒すべき症状がある場合には、胃カメラによる精密検査が強く推奨されます。一方、若年で典型的な症状の場合などはまず薬物治療を試み、必要に応じて後日内視鏡検査を行うこともあります。必要によっては大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)をおこなうことも検討されます。
また、機能性ディスペプシアの診療ではピロリ菌の検査も重要です。日本人は中高年を中心にピロリ菌感染者が多く、ピロリ菌が胃にもたらす影響とFD症状との関連が指摘されています。そのためFDが疑われる場合、まずピロリ菌に感染していないか調べます。ピロリ菌陽性であれば胃がん予防の観点からも除菌治療を行い、その後症状の経過をみてFDかどうかを判断します(ピロリ菌を除菌した結果症状が治まれば、診断名は「ピロリ菌関連胃炎による消化不良」となる場合もあります)。ピロリ菌がいない、あるいは除菌後も症状が続く場合に機能性ディスペプシアと確定診断されます。
機能性ディスペプシアの治療法
FDの治療は主に薬物療法と生活習慣の改善が中心になります。まず、患者さん本人が病気を正しく理解し、FDに詳しい主治医の指導のもとで治療を継続することが大切です。症状が長引くと不安になりがちですが、医師を信頼して治療に取り組むことでより良い結果につながります。以下、生活上の注意点と薬物療法について詳しく説明します。
・生活習慣の見直し
生活リズムや食習慣の改善はFD治療の基本です。実際、FD患者さんには睡眠不足や運動不足、不規則な食事時間や偏った食事など生活習慣の乱れがみられることがあり、これらを整えることで症状が改善するケースもあります。具体的には「満腹になるまで一度に食べず、少量ずつ分けて食事をとる」ことが勧められます。脂っこい料理や高カロリーの食品は胃もたれや痛みを起こしやすいため避け、高脂肪食を控えることも有用です。さらに、アルコールやカフェイン(コーヒー)の摂取を控え、喫煙者はこの機会に禁煙しましょう。規則正しい食生活と十分な睡眠・適度な運動を心がけることで、胃腸の働きが整い症状緩和につながることが期待できます。ストレスも症状を悪化させるため、リラクゼーションや趣味の時間を持つ、必要に応じて心理カウンセリングを受けるなどストレスケアも取り入れてください。
・薬物療法(内服薬)
FDの症状に対しては、作用の異なる以下の3種類の薬が第一選択肢として用いられます。
- 胃酸分泌を抑える薬 – プロトンポンプ阻害薬(PPI)やH2ブロッカー(H2受容体拮抗薬)といった胃酸を抑制する薬です。胃酸による粘膜刺激や胃酸過多が症状に関与している場合、このタイプの薬で胃酸の分泌を抑えるとみぞおちの痛みや灼熱感の改善が期待できます。消化性潰瘍の治療薬としても使われる安全性の確立した薬剤です。
- 消化管運動機能改善薬 – 胃の動きを良くする薬剤です。日本では アコチアミド(商品名アコファイド®)が機能性ディスペプシア治療薬として承認されています。この薬は胃排出能を高め、胃の運動リズムを整える作用があり、胃に内容物が長時間停滞するタイプのFDで有効です。実際、食後のもたれ感や早期満腹感などの改善に寄与することが確認されています。
- 漢方薬(六君子湯など) – 漢方製剤では六君子湯(りっくんしとう)がFDによく用いられます。六君子湯は胃の運動機能を改善するだけでなく、不安感を和らげる作用も報告されており、ストレスが関与する患者さんにも有用です。そのほか症状や体質に応じて別の漢方薬が処方されることもあります。
これらの薬は単独または併用で処方され、患者さんの症状や反応を見ながら調整していきます。ピロリ菌感染が判明している場合は、まず除菌治療を行った上で上記の薬物療法を検討します。ピロリ菌の除菌によって症状が改善するケースもあるため、感染がある場合には除菌がFD治療の一環となります(※前述のとおり除菌効果が現れるまでにタイムラグがある点には留意が必要です)。 なお、初期治療(PPI・アコチアミド・六君子湯など)で十分な効果が得られない場合、第二選択として以下のような治療が検討されます。
- 抗不安薬・抗うつ薬の少量投与: 心身症的な側面が強い患者さんには、抗不安薬(例えばソラナックス®等)や低用量の抗うつ薬(例えばトリプタノール®等)を用いることで不安・抑うつ状態を改善し、それに伴い胃の不調が和らぐことがあります。これらはいわゆる脳腸相関に働きかける治療です。
- 別の種類の消化管運動改善薬: アコチアミドで効果が不十分な場合、他の機序の消化管運動促進薬(胃腸薬)を試すこともあります。医師が症状や副作用プロファイルを考慮して選択します。
- 他の漢方薬: 六君子湯以外にも、証(患者の漢方医学的な体質)に合わせて処方を変えることで効果が見られる場合があります。
これらの治療を組み合わせてもなお症状が続く場合には、改めて他の病気が隠れていないか詳しく検査したり、心療内科の専門医と連携して心理的アプローチ(認知行動療法など)を行ったりすることもあります。FDは症状が慢性に経過することも多いですが、あきらめず医療者と二人三脚で治療を続けることが重要です。
治療のゴールと注意点
機能性ディスペプシアは命に関わる深刻な病気ではありませんが、症状が長引けば日常生活に支障を来すことがあります。しかし適切な治療によって多くの患者さんで症状の改善が期待できます。すぐに完全に治るとは限りませんので、「まずは症状を今より軽くする」ことを目標に根気強く取り組みましょう。主治医との信頼関係を保ち、生活習慣の改善と薬物療法を地道に続けていくことで、少しずつ胃の調子が整い生活の質も向上していくはずです。症状がつらいときは無理をせず、早めに消化器内科を受診して専門的な診断・治療を受けることをお勧めします。日々の工夫と適切な医療によって、機能性ディスペプシアとうまく付き合っていくことが可能です。



