2025年05月14日
健康診断などでピロリ菌が陽性とわかったものの、「症状もないしそのまま放置している」という方はいませんか? また、これまで一度もピロリ菌検査や胃カメラ検査を受けたことがないという方も要注意です。ピロリ菌は胃の中に住み着く細菌で、放置すると慢性胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍だけでなく、将来的に胃がんにつながる可能性もある恐ろしい菌です。今回はピロリ菌とは何か、その放置の危険性や検査方法、そして早期に除菌治療を行う必要性について、丁寧にわかりやすく解説します。30歳以上の皆さんは特に、この機会にぜひピロリ菌への理解を深めてください。
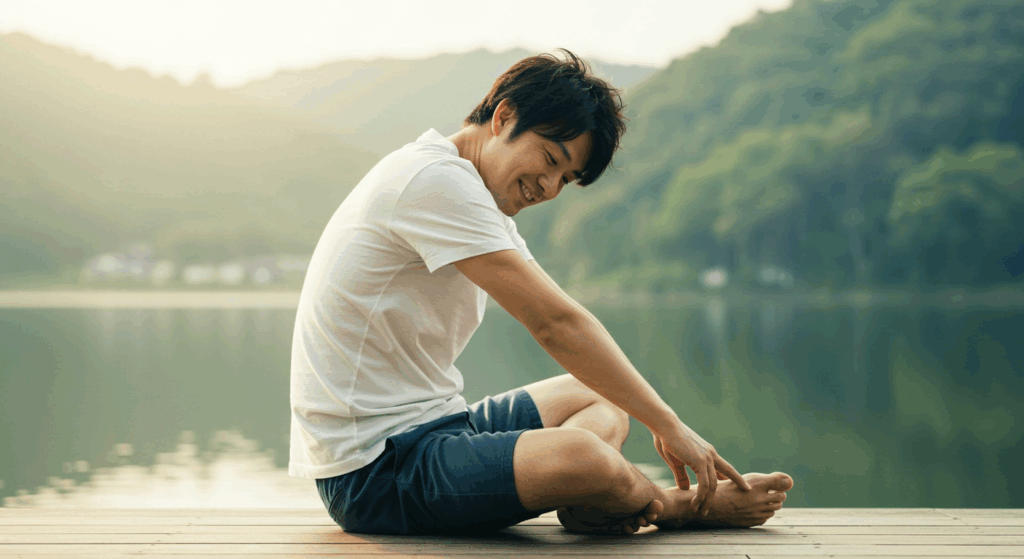
ピロリ菌とは?感染経路と世代別の感染率
ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)とは、胃の粘膜に住みつく細菌です。強い酸性の胃の中でも生きられる特殊な菌で、多くの場合は幼少期に感染し、そのまま胃に住み続けます。感染経路は主に経口感染で、かつては衛生状態の悪い井戸水などを介して感染することが多く、また家族内感染(特に親が噛み砕いた食べ物を子に与える「口移し」)によって広がることが知られています。乳幼児期は免疫機能が未熟なため感染しやすく、一度定着すると自然には消えません。
日本では世代によってピロリ菌の感染率に大きな差があります。衛生環境が整っていなかった時代に幼少期を過ごした現在60代以上の方では、実に「2人に1人」がピロリ菌に感染しているとの報告があります。例えば1950年代生まれ(現在70代前後)の感染率は約60%にも達します。一方、衛生環境の改善した現代では若い世代の感染は減少傾向で、1990年以降生まれの20代では感染率は数%程度と非常に低くなっています。年齢が高いほど感染者が多いため、30歳以上の方は「自分も感染しているかも?」と一度疑ってみることが大切です。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000167150.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/106/1/106_10/_pdf
ピロリ菌を放置する危険性:胃炎・胃潰瘍・胃がん
ピロリ菌に感染していても、感染直後には自覚症状がないことがほとんどです。しかし胃の中では静かに炎症が進行しています。若い頃にピロリ菌に感染するとまず胃粘膜に急性の炎症が起こり、その後慢性的な胃炎へと移行します。ピロリ菌を放置して長年にわたり感染が続くと、胃粘膜の炎症が慢性化(萎縮性胃炎)し、やがて胃潰瘍や十二指腸潰瘍を発症するリスクが高まります。実際、ピロリ菌感染者は非感染者に比べて胃・十二指腸潰瘍を起こしやすく、再発もしやすいことが知られています。
さらに深刻なのは胃がんのリスクです。現在、日本人の胃がんの9割以上はピロリ菌感染が原因とまで言われています。長期感染により萎縮性胃炎が進行すると、胃粘膜の防御機能が低下し遺伝子にダメージが蓄積しやすくなるためと考えられています。「ピロリ菌がいないと胃がんにならない」と断言はできませんが、実際にピロリ菌に未感染の人が胃がんになるケースはごくわずか(全胃がんの1〜2%程度)と言われています。ピロリ菌感染者は未感染者に比べ格段に胃がんになりやすいのです。
また、ピロリ菌感染は胃がん以外にも胃MALTリンパ腫(粘膜関連リンパ組織リンパ腫)という特殊な胃のリンパ腫の発症要因にもなります。こちらはピロリ菌を除菌することで治癒が期待できるタイプの腫瘍です。いずれにせよ、ピロリ菌をそのままにしておくことは将来的に重大な病気につながる危険性があります。症状がないからと放置せず、早めに対処することが重要です。
胃痛👇
https://ykhm-cl.com/wp/symptom/symptom03/
胃もたれ👇
https://ykhm-cl.com/wp/symptom/symptom04/
胸焼け👇
https://ykhm-cl.com/wp/symptom/symptom05/
ピロリ菌の検査方法(抗体検査・尿素呼気テスト・内視鏡検査)
「自分がピロリ菌に感染しているか調べたい」と思ったら、いくつかの検査方法があります。大きく分けると内視鏡を使わない検査と、胃カメラなど内視鏡を使う検査に分類されます。
内視鏡を使わない検査として代表的なのは次の二つです:
- ピロリ菌抗体検査(血液検査):血液あるいは尿を採取して、ピロリ菌に感染していると体内で作られる抗体の有無を調べる方法です。比較的手軽で費用も安いため、健康診断のオプション検査として採用されることもあります。結果が陽性なら「現在もしくは過去にピロリ菌に感染したことがある」ことを示します。ただし過去に除菌済みでも抗体が残存して陽性になる場合があるため、現在感染しているかの判定には慎重な解釈が必要です。
- 尿素呼気テスト(尿素呼気試験):ピロリ菌が出す酵素「ウレアーゼ」の働きを利用した検査です。検査薬の入った特殊な薬剤(13C尿素)を服用し、15〜20分後の呼気(吐く息)を集めて調べます。ピロリ菌が胃にいると薬剤の尿素が分解されて二酸化炭素が発生するため、呼気中の二酸化炭素の変化で感染の有無を判定します。苦痛もなく精度も高いため、今後主流になる検査方法と言われています。主に除菌治療後の効果判定(ピロリ菌が消えたかどうかの確認)にも用いられます。
このほかにも、便中抗原検査(便を調べてピロリ菌の抗原を検出する方法)も内視鏡を使わない検査として有効です。いずれの非内視鏡検査もメリットは体への負担が少ない点ですが、陽性だった場合は内視鏡検査で直接胃の状態を調べることが推奨されます。
内視鏡を使う検査としては、胃カメラ(胃内視鏡)を挿入して胃の中を観察しながら行う方法があります。内視鏡検査時に胃の粘膜の一部を生検採取して調べることで、ピロリ菌を直接検出することができます。具体的には、採取した組織を試薬につけて色の変化を見る迅速ウレアーゼ試験(ピロリ菌がいればアンモニアが発生し色が変わる)や、顕微鏡で菌体を見る鏡検法、培養して増殖を確認する培養法などがあります。内視鏡検査はこれらの確定診断に加え、後述するように胃粘膜の状態も直接チェックできるため、陽性の場合は一度受けておくと安心です。「内視鏡検査でピロリ菌感染はわかりますか?」という疑問に対して、日本消化器内視鏡学会も「内視鏡検査中に組織を採取し上記の検査を行うことで確定診断できる」と回答しています。つまり胃カメラをすればピロリ菌の有無もその場で調べられるということです。
https://ykhm-cl.com/wp/medical/medical04/
胃カメラ検査でわかること
ピロリ菌の有無を確認するだけなら血液検査や呼気検査で可能ですが、胃カメラ検査(内視鏡検査)にはそれ以外の大きなメリットがあります。それは、胃そのものの状態を詳しく観察できる点です。胃カメラでは食道から胃、十二指腸に至るまで直接カメラで粘膜を観察できるため、以下のような病変の有無をその場でチェックできます。
- 逆流性食道炎や食道裂孔ヘルニアなど食道の異常
- 慢性胃炎(萎縮性胃炎)の程度(ピロリ菌感染による粘膜の萎縮状況)
- 胃ポリープ(良性の粘膜の隆起)や胃潰瘍・十二指腸潰瘍の有無
- 早期の胃がんや食道がんなどの腫瘍性病変の発見
- ヘリコバクター・ピロリ感染症の有無(胃粘膜の所見からある程度推測可能で、必要に応じて生検で確定診断)
特に胃がんは早期には自覚症状がほとんどないため、内視鏡による早期発見が重要です。ピロリ菌に長年感染して胃炎が進んでいる方は、粘膜が萎縮して平坦になるため、内視鏡医が見れば「ピロリ菌のいる胃」か「いない胃」か概ね見分けがつきます。ピロリ菌未感染の胃粘膜はひだが細くまっすぐでツヤがありますが、感染胃では粘膜がデコボコして赤みを帯び、ひだが太く不規則になります。こうした所見も含め、胃カメラ検査は単にピロリ菌を「検査する」だけでなく、胃の健康状態を総合的に評価する検査と言えます。
「胃カメラは苦しいから嫌だ」と敬遠される方もいるかもしれません。しかし次の章で述べるように、現在では苦痛の少ない胃カメラ検査が可能です。当クリニックでもできるだけ楽に検査を受けていただける工夫をしていますので、ご安心ください。
https://ykhm-cl.com/wp/gastrocamera/gastrocamera01/
ピロリ菌の除菌治療:必要性と方法
もしピロリ菌検査で陽性と判明したら、基本的には除菌治療(ピロリ菌を薬で退治すること)を行うことが推奨されます。ピロリ菌を除菌すれば、前述した胃潰瘍の再発予防や胃がんリスクの低減につながるためです。日本でも2013年以降、ピロリ菌感染による慢性胃炎に対する除菌治療が保険適用となり、陽性であれば積極的に治療する流れになっています。
除菌の方法は、お薬を飲むだけで完了します。一般的には一次除菌療法として、「プロトンポンプ阻害薬(胃酸の分泌を抑える薬)」と「2種類の抗生物質」を1日2回ずつ、7日間服用します。具体的な薬剤名としては、胃酸を抑えるラベプラゾール等に加え、抗生剤のアモキシシリン+クラリスロマイシンの組み合わせが一次除菌で用いられることが多いです。1週間薬を飲み切った後、1〜2か月ほど期間をあけてから尿素呼気テスト等でピロリ菌が消えたか確認します。
一次除菌でピロリ菌が十分に除去できなかった場合(一次除菌失敗)は、薬を変更した二次除菌療法を行います。二次除菌では胃酸抑制薬+アモキシシリン+メトロニダゾールという別の抗生剤の組み合わせで、同じく1日2回・7日間の服用を行います。二次まで行っても除菌できないケースは稀ですが、さらに三次除菌以降の手段も一応用意されています(専門医療機関での培養感受性検査に基づく治療など)。
除菌治療の成功率は、一次除菌でおおよそ80%前後と言われます。日本人の場合、クラリスロマイシン(マクロライド系)に対する耐性菌が増えてきているため、一次成功率がやや下がってきています。しかし一次で除菌できなかった人も二次除菌でほとんど成功し、最終的に95%以上の方はピロリ菌の除去に成功します。除菌に使う薬はすべて保険が適用されますし、治療費の自己負担(3割負担の場合)も1万円程度と、将来の病気予防の「投資」としては決して高くありません。何より一回の検査と一週間の服薬で、将来の胃がんリスクを大きく減らせるのは驚くべきことです。

一般的に使用される除菌薬の一例です。シート状になっており、飲み忘れを防ぎます。
https://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_med?japic_code=00066207
除菌治療の副作用と成功率
除菌治療に使う抗生物質や胃酸抑制薬による副作用は、一般的に軽度なものが多いです。抗生物質の内服でよくある副反応としては下痢や軟便、お腹の張りといった胃腸症状、あるいは味覚の変化(苦みを感じる、金属っぽい味がする等)や発疹が稀に起こることがあります。ただし、これらの症状は服用期間中〜終了直後の一時的なもので、重篤な副作用は非常にまれです。万一強い副作用が出た場合は速やかに主治医に連絡する必要がありますが、大半の方は多少お腹がゆるくなる程度で問題なく飲みきれるようです。
クラリスロマイシンを含む一次除菌薬では、飲んでいる間に苦みを感じることがあります(味覚異常の副作用)が、これも服薬終了とともに改善します。また、二次除菌で用いるメトロニダゾールという抗生剤は、服用中にアルコールを摂取すると顔のほてりや動悸を引き起こすことがあるため、除菌期間中の飲酒は禁止とされています。こうした注意点はありますが、基本的には除菌治療は安全かつ効果的です。医師の指示通り服薬し終えた後は、きちんとピロリ菌が除去できたか再検査(尿素呼気テスト等)を受けるのも忘れないことが重要です。
除菌後の再感染リスクと定期検診の重要性
無事にピロリ菌の除菌に成功した後は、「もう二度とピロリ菌の心配はいらないの?」という点が気になりますよね。結論から言えば、再感染のリスクは極めて低いとされています。ピロリ菌は主に幼少期に感染する菌であり、日本の衛生環境では成人が新たに感染する可能性はごく低いためです。実際、除菌に成功するとその後再びピロリ菌に感染する危険性はほぼありません。ただし、まったくゼロではないので注意は必要です。例えばご家族にまだピロリ菌保菌者がいる場合、そこから経口的にうつるリスクは考えられます。また海外の衛生状態の悪い地域に滞在して感染した例も報告されています。しかし過度に心配する必要はなく、基本的には「一度除菌すれば再発しない」と考えてよいでしょう。
一方で、除菌すれば胃がんのリスクもゼロになるのか?というと、残念ながら完全にゼロにはなりません。除菌によって胃がんになる可能性は大きく下がりますが、長年の感染で既に胃粘膜にダメージ(萎縮や腸上皮化生など前がん状態)が蓄積していた場合、その後も一定のリスクは残存します。特に除菌時に小さすぎて発見できなかった早期胃がんが既に存在しているケースもあり得るため、除菌後も定期的な内視鏡検査(胃カメラ)を受け続けることが推奨されます。胃がんリスクの高い人(除菌時に高度萎縮がある人や高齢の人)は除菌後5年間は年1回のペースで胃カメラ検査を受け、それ以降も医師と相談の上で継続していくことが望ましいとされています。比較的若く除菌できた人でも、「除菌したからもう検査はしなくていい」わけではないことに注意しましょう。
定期検診では、胃カメラのほかピロリ菌再感染がないかのチェックも兼ねて、必要に応じて尿素呼気テスト等を行う場合があります。せっかくピロリ菌を退治しても、その後のフォローを怠って胃がんを見逃しては本末転倒です。除菌後も油断せず、胃の定期チェックを続けることが長期的な安心につながります。
まとめ
ピロリ菌は放置すると将来的に大きなリスクを伴う菌ですが、検査で発見し適切に除菌すれば怖がる必要はありません。30歳以上でピロリ菌陽性を指摘されたままの方や、一度も検査を受けたことがない方は、この機会にぜひ一度チェックしてみてください。そして陽性だった場合でも落ち着いて、信頼できる医療機関で治療を受けましょう。当院でも苦痛の少ない内視鏡検査と的確な治療で、皆様の「ピロリ菌退治」をお手伝いいたします。胃を守る第一歩として、ピロリ菌を放置せず検査と治療を受けることを強くおすすめします。あなたとご家族の胃の健康が末永く守られるよう、私たちがお力になります!



