2025年05月14日
最近、原因がはっきりしないまま胃の痛みや胃もたれが続いていませんか?内視鏡検査など詳しい検査を受けても特に異常が見つからないのに、胃の不快感が消えず困っている…そんな場合、機能性ディスペプシアという病気が隠れているかもしれません。機能性ディスペプシア(Functional Dyspepsia: FD)は、胃や腸に目立った炎症や潰瘍などの異常がないにもかかわらず慢性的な胃の症状が続く状態を指します。決して珍しい病気ではなく、日本人の約15%(およそ6~7人に1人)が経験すると報告されている頻度の高い病気です。命に関わるものではありませんが、症状が長引くと食事や日常生活を思い切り楽しめず、つらいですよね。だからこそ、我慢しすぎずにきちんと対処することが大切です。
腹痛について👇
https://ykhm-cl.com/wp/symptom/symptom01/
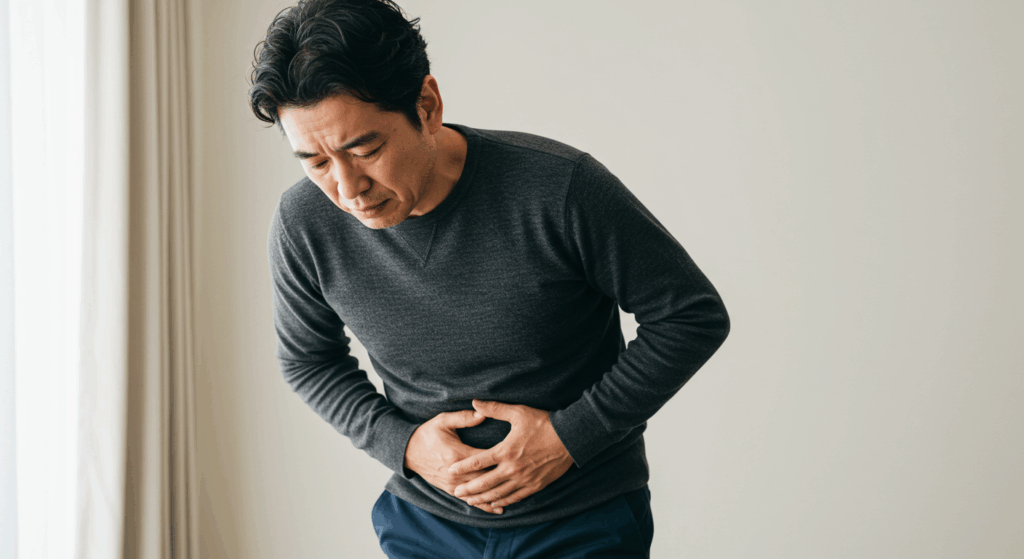
機能性ディスペプシアとはどんな病気?
機能性ディスペプシア(FD)とは、胃の働きの異常によって起こる慢性的な胃の不調のことです。具体的には、胃のあたり(みぞおち付近)の痛みや不快感、食後の重苦しさ(胃もたれ)、少し食べただけですぐ満腹になってしまう感じなどの症状が繰り返し現れます。それにもかかわらず、胃カメラ(上部内視鏡検査)やエコー検査、血液検査などで胃に器質的な異常(炎症・潰瘍・腫瘍など)が見当たらないのが特徴です。いわば「胃の調子がうまく働いていない状態」であり、検査で原因が見えないために周囲には理解されにくいかもしれません。しかし、症状は本人にとって紛れもない現実であり、適切な治療で改善が期待できるれっきとした病気です。
機能性ディスペプシアの症状の現れ方にはいくつかパターンがあります。大きく分けると食後に症状が強く出るタイプと、空腹時にも痛みが出るタイプがあります。前者は食事のあとに胃が重くもたれる、食べ始めにすぐお腹いっぱいに感じる(早期満腹感)といった症状が中心で、医学的に「食後愁訴症候群(PDS)」と呼ばれます。後者はみぞおちの痛みや焼けるような不快感が主で、食事に関係なく空腹時にも起こるのが特徴です(「心窩部痛症候群(EPS)」と呼ばれます)。多くの場合はこれらが混在しますが、いずれにしても胃の痛みや胃もたれなどで日常生活に支障が出る点では共通しています。
https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/pdf/fd2021r_.pdf
主な症状とお悩みのサイン
機能性ディスペプシアでは、以下のような症状がみられます。思い当たるものはありませんか?
- 胃の不快感・重み(常に胃が重苦しい感じがする)
- 食後の胃もたれ(食事のあと胃がいつまでもスッキリしない)
- 少量で満腹(食べ始めてすぐ満腹になり、それ以上食べられない)
- みぞおちの痛み(シクシク、キリキリと胃が痛む)
- みぞおちの灼熱感(胃のあたりが焼けるように感じる)
- 吐き気やムカムカ(実際に吐くことは少ない)
- げっぷや腹部の膨満感(お腹が張って苦しい)
これらの症状は一時的な胃の不調でも起こり得ますが、機能性ディスペプシアではこうした症状が慢性的(継続的)に続くことがポイントです。症状はストレスを感じたときや緊張したときに悪化しやすい傾向もあります。「胃の調子が悪いけど検査では異常なしと言われた…」という方は、この機能性ディスペプシアの可能性があります。
加えて、機能性ディスペプシアの方は胃の症状だけでなく、全身の不調を伴うこともあります。たとえば肩こりや倦怠感、めまい、手足の冷え、背中の痛みなど、自律神経の乱れに関連した症状がみられるケースもあります。胃の不調とともにこうした症状がある場合、ストレスなどによる自律神経への影響が関与しているかもしれません。
胃痛について👇
https://ykhm-cl.com/wp/symptom/symptom03/
胃もたれについて👇
https://ykhm-cl.com/wp/symptom/symptom04/
胸焼けについて👇
https://ykhm-cl.com/wp/symptom/symptom05/
吐き気、嘔吐について👇
https://ykhm-cl.com/wp/symptom/symptom06/
考えられる原因は?
なぜ検査で異常がないのに胃痛や胃もたれが起きるのでしょうか。原因は一つではなく複数の要因が重なって胃の機能に影響していると考えられています。主な原因要因には以下のようなものがあります。
- ストレスや心因的要因:精神的ストレスや緊張が続くと自律神経のバランスが崩れ、胃の働きが乱れます。緊張すると胃がキリキリ痛んだり、ストレスで胃が重く感じたりするのはこのためです。現代社会ではストレス性の胃の不調に悩む方が非常に多く、機能性ディスペプシアとも深く関係しています。
- 胃の運動機能低下:本来、胃は食べ物を一時的にためてからゆっくりと十二指腸へ送り出すポンプの役割を持ちます。しかし胃の運動機能(ぜん動運動)が低下すると、食べ物を適切に送り出せず胃に長く停滞してしまい、胃もたれや膨満感の原因になります。加齢や不規則な生活習慣、過食なども胃の動きを鈍らせる一因です。
- 胃の知覚過敏:胃自体が敏感になっている状態です。通常なら問題にならない少量の食事や胃酸にも過敏に反応し、痛みや不快感を感じてしまいます。これはストレスや生活習慣の乱れによって胃と脳をつなぐ自律神経の調整がうまくいかなくなることで起こると考えられています。
- 胃酸の分泌過多:胃酸が過剰に出過ぎると胃の粘膜を刺激し、胃痛や灼熱感の原因となります。特に空腹時の胃痛が強いタイプでは胃酸過多が関与している場合があります。
- 生活習慣・嗜好品:暴飲暴食や脂っこい食事、早食い、寝る前の飲食、不規則な睡眠などの生活習慣の乱れは胃の機能低下に直結します。また、過度の飲酒や喫煙習慣も胃粘膜を荒らし運動機能を低下させるため、症状を悪化させる要因です。
- その他の要因:ピロリ菌感染や過去の胃腸炎(感染症)がきっかけで発症する場合や、遺伝的な要因、うつ病・不安障害などメンタル面の不調が関連しているケースもあります。ピロリ菌については、感染があると胃の不調を引き起こしやすいため、除菌療法が有効な場合があります。
このように機能性ディスペプシアは様々な要因が絡み合って起こるため、「これさえ直せば治る」という単純なものではありません。ただし、生活習慣の改善やストレスケアによって症状が軽減することも多く、原因に合わせた適切な治療で症状改善・再発予防が期待できます。
診断と検査:まずは胃カメラでチェック
慢性的な胃の痛みや胃もたれがある場合、まず大切なのは他の病気が隠れていないか確認することです。症状だけでは胃潰瘍や胃炎、場合によっては胃がんなどとの区別がつかないため、医療機関で検査を受けることをおすすめします。消化器内科では主に胃カメラ検査(上部消化管内視鏡検査)によって胃の中を直接観察し、粘膜の炎症や潰瘍の有無を詳しく調べます。胃カメラに加えて血液検査でピロリ菌感染の有無を確認したり、腹部エコー(超音波)検査で胆のうや膵臓など他の臓器に異常がないかをチェックすることもあります。必要に応じて大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)を行い、症状の原因となりうる腸の病気(例えば過敏性腸症候群や潰瘍性大腸炎など)がないか確認することも可能です。
こうした検査の結果、胃や消化管に明らかな病変が認められず、それでも症状が続いている場合に機能性ディスペプシアと診断されます。裏を返せば、機能性ディスペプシアは「検査で異常がないことを確認して初めて診断できる」病気です。長引く胃の症状に悩んでいる方は、自己判断で「ただの胃もたれだろう」と放置せず、一度きちんと検査を受けておくと安心です。
https://ykhm-cl.com/wp/medical/medical04/
「胃カメラは苦手…」という方もご安心ください。当院では経鼻内視鏡と呼ばれる細いスコープを鼻から挿入する方法や、鎮静剤を使った内視鏡検査にも対応しており、できるだけ苦痛の少ない検査を心がけています。過去に胃カメラでつらい思いをされた方や初めての内視鏡検査で不安な方でも、リラックスして受けていただけるよう配慮しています。「検査が怖い」という方は遠慮なくご相談ください。
https://ykhm-cl.com/wp/gastrocamera/gastrocamera01/
治療と対処法:生活習慣の見直し+お薬で改善を目指そう
機能性ディスペプシアの治療は、大きく生活習慣の改善と薬物療法(飲み薬による治療)の二本立てで行います。原因や症状の現れ方は人それぞれですが、まず共通して取り組みたいのが日々の習慣の見直しです。
生活習慣の改善
胃に優しい生活を心がけましょう。具体的には、暴飲暴食を避けて腹八分目を守る、よく噛んでゆっくり食事をする、脂肪分や糖分の多い食品は控える、刺激物(香辛料やカフェイン)の摂取を減らす、飲酒は適量にとどめ禁煙を検討する、といった点がポイントです。特に下記のような食品・飲み物は症状悪化につながりやすいため摂りすぎに注意しましょう。
- 脂っこい料理(天ぷら、フライなど)
- 消化に時間がかかる食べ物(餅やこんにゃく、きのこ類など)
- 甘いお菓子やスイーツ類
- 香辛料の強い刺激物(唐辛子、ニンニクなど)
- カフェインを多く含む飲み物(ブラックコーヒー、濃いお茶、エナジードリンク)
- アルコール飲料(ビール、ワイン、日本酒など)
- 柑橘系の果汁を多く含む酸っぱい飲み物(オレンジジュース、グレープフルーツジュースなど)
また、十分な睡眠と適度な運動も大切です。睡眠不足や運動不足は自律神経のバランスを乱し、胃腸の働きを鈍らせてしまいます。規則正しい生活リズムを作り、ストレスを溜め込まないよう適度に発散する工夫もしてみましょう。例えば、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かってリラックスしたり、軽い散歩やストレッチで体を動かすだけでもストレス解消に役立ちます。
薬物療法(飲み薬による治療)
生活改善と並行して、症状に応じたお薬で胃の調子を整えていきます。機能性ディスペプシアの治療薬にはいくつか種類がありますが、まず症状のタイプに合わせたお薬を選択するのが一般的です。例えば、みぞおちの痛みや灼熱感が強いタイプの方には胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬(PPI)やH2ブロッカーなど)が第一選択となります。一方、食後の胃もたれや早期満腹感が主な方には胃腸の動きを良くする薬(消化管運動機能改善薬)が効果的です。これらのお薬によって、乱れた胃の働きを正常化し、胃酸の過剰分泌や胃内容物のうっ滞を改善していきます。
症状や原因に応じて、その他にも以下のような薬剤を組み合わせることがあります。
- 胃粘膜保護薬:胃の粘膜を保護し、刺激から守るお薬です。胃酸によるダメージを和らげ、胃痛やむかつきを軽減します。
- 漢方薬:体質改善や症状緩和を目的に用いられるお薬です。機能性ディスペプシアに対しては、胃腸の働きを整える六君子湯(りっくんしとう)などの漢方が効果を発揮することがあります。漢方薬は全身のバランスを整えるアプローチで、西洋薬と併用するケースもあります。
- 抗不安薬・抗うつ薬:ストレスや不安感が強く胃症状に影響している場合に用いることがあります。いわゆる「安定剤」「抗うつ剤」の一部で、胃と脳の連絡(脳腸相関)に作用し症状を和らげます。少量から開始して不安感を緩和することで、結果的に胃の調子も改善していくことが期待できます。
- ピロリ菌の除菌薬:検査でピロリ菌感染が確認された場合、除菌治療(胃薬と複数の抗生物質の内服)を行うことで症状が改善することがあります。ピロリ菌は胃の慢性的な炎症を引き起こすため、除菌により胃の環境が整えばディスペプシア症状の軽減につながることがあります。
これらの治療はすべて保険診療の範囲内で受けることができますので、「費用が心配…」という場合も安心です。患者さん一人ひとりで症状の現れ方や抱えている不安は異なります。専門機関にて一人ひとりに合ったお薬の組み合わせや治療を相談することをお勧めします。



